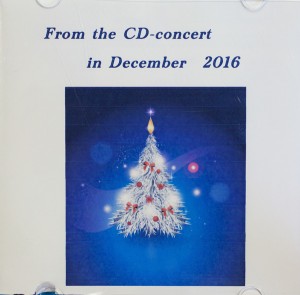
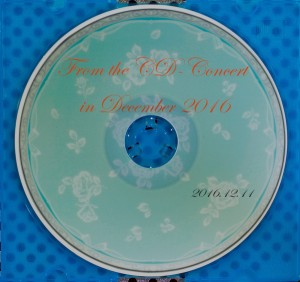 さて、早いもので(ほんと、この歳になると年の瀬が来るのが毎年早まっているような気がします)今年も師走のCDコンサートを迎えました。
さて、早いもので(ほんと、この歳になると年の瀬が来るのが毎年早まっているような気がします)今年も師走のCDコンサートを迎えました。
25回目を迎えたこのコンサート、今回は7名の参加で、参加してくださる方はもう常連の方が多く、たまに一方くらい新規の方がみえます。 それがまた楽しみです。中には、この集まりが師走の風物詩のように思ってくださる方もいて、なんだかその方の生活の一部になっているようで、開催側の冥利に尽きます。
今年のプログラムは、下記の通りです。
ちょっと土地の匂いのする曲を中心に視聴していただきました。
実はこのプログラムの前に、江差追分とドップラーのハンガリー田園幻想曲をネット動画で流して、その趣旨を感じていただきました。
シルクロードで繋がっているような、単なる偶然のような。
Izzyのこぶしの利いた歌い回し、M.マチューの「r」の極端な巻き舌も、その土地独特のものとしてご紹介いたしました。
———————Program—————
- A.ヴィヴァルディ作曲 協奏曲集「四季」
D.ゼペック(Vn&Dir.)
ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ベルリン
- J.S.バッハ作曲 イギリス組曲No.3 ト短調 BWV 808
ルドルフ ブッフビンダー(P)
- G.F.ヘンデルLascia Ch’io Pianga
The Last Rose Of Summer
Izzy (vocal)
- スメタナ作曲 交響詩「モルダウ」
ベルリン・フィル ワルトビューネコンサートから
ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 (BD)
- J.ハイドン作曲 弦楽四重奏曲No.77 ハ長調 op.76-3「皇帝」
イタリア弦楽四重奏団
- E.ラロ作曲 スペイン交響曲 op.21
オーギュスタン・デュメイ(Vn)
ミシェル・プラッソン指揮
トゥールーズ・カピトール管弦楽団
7.ミレイユ ・マチュー (「エディット・ピアフ」から)
バラ色の人生 群衆
- ア・カペラ(フィンランドの賛美歌集より)
あなたに感謝します、わたしの神よ
我が主よ、あなたに向かって
タウノ・サトマー指揮 カンドミノ合唱団













