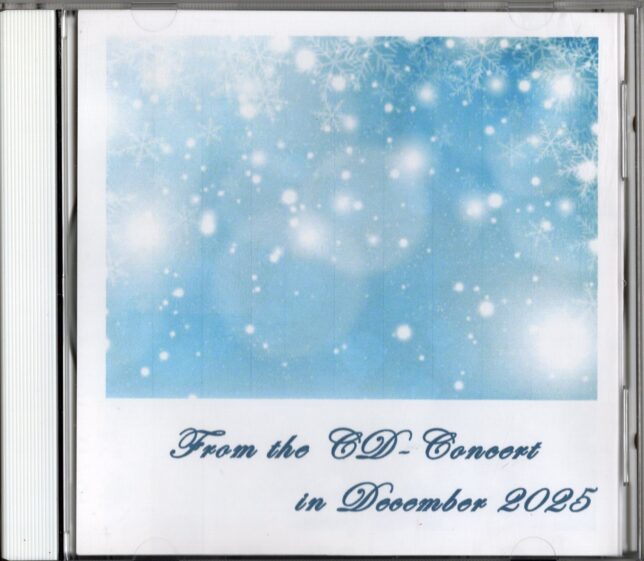次は、秋田県と山形県について。
秋田の名は、米の「あきたこまち(平仮名)」の名前からも、由来は容易に想像できる。
と思いきや、調べてみるとそう単純な由来ではないらしい。
一説では、低湿地で農業に不向きな「悪田(あくでん)」を意味する「飽田(あきた)」から始まり、奈良時代に「秋田」という漢字が当てられたといわれている。
また、出羽国に古代からある秋田郡からという説。
平安時代に編纂された「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」(日本最古の辞書)では、秋田の読みは「あいた」とある。
さらに古くは「あぎた」と読んでいた。
「秋田」の字は当て字なので、「秋』は地名の由来とは無関係。
秋田の地名由来は、「あぎ」は「上げ」から転じたもので、高くなっている土地を意味する。
「た」は場所を意味する「と」が転訛したもの。
つまり「秋田」の名前の由来は「(周辺よりも)高くなっている場所」という説。
さらに、飛鳥時代の斉明天皇4年(658年)に阿倍比羅夫の日本海遠征の際、この地を訪れ地名を「齶田(あぎた)」と報告したことに由来するというもの。「齶田(あぎた)」はアゴに似た地形からつけられたともいわれており、雄物川河口部の古い地形のことを示しているとの説もある。
さて、私が小学校の頃、日本で一番広い湖は琵琶湖、2番目は八郎潟、3番目が霞ヶ浦と習った記憶がある。男鹿半島のつけ根に、大きなうろのような八郎潟があった。ちなみに八郎潟は今でも秋田県にある。が、干拓で面積は当初の20%になり今やその存在感は薄れてしまった。
この頃、つまり60年前は日本の人口の増加傾向が続き、その食料需要に対応するため、しきりに干拓が行われた。今の減反政策とは真逆の農政である。特に、秋田県の八郎潟と岡山県の児島湾が有名だった(覚えがある)。潟というくらいだから遠浅で、干拓には好都合だったのだろう。今は大潟村として、かつての広く浅い湖の名残りがかすかに村名に残されている。
八郎潟の名前の由来は、人から龍へ姿を変えられた八郎太郎が棲家としたという伝説によるとされている。
次に、秋田には能代、米代川と、「代」がつく地名がある。
歴史は古く、「日本書紀」に、「斉明天皇4年(658年)4月、越国守阿倍比羅夫が軍船180隻を引いて蝦夷を伐つ、齶田(飽田)・渟代二郡の蝦夷望み恐じて降わんと乞う」と、渟代の名が出てくる。当時の読みである「ヌシロ」の地名の由来を、アイヌ語で「台地の上の草原地」を意味する「ヌプシル」(nup-sir) からの転訛とする説もあるが、秋田の地名の由来とも合致する。
その後「続日本記」では、「渟代」から「野代」へと表記が変わっている。
野代から現在の能代への漢字の変遷は、元禄7年(1694年)および宝永元年(1704年)に大震災が起こり、「野代」という地名が「野に代わる」と読めることから、「よく代わる」と読める「能代」と改めたとある。
もう一つ、「代」がつく名前に米代川がある。雄物川と並ぶ秋田県の大河だが、米代川の語源は「米のとぎ汁のような白い川」からとの説がある。
上流に住んでいた人たちが川で米をといで川が白くなったという説や、源流にいただんぶり長者(だんぶり=トンボ 地域の伝説の長者)の米のとぎ汁だとする伝説もある。また、915年、十和田湖火山が大噴火を起こした際の火砕流や火山灰で白く濁った川の色が語源との説も。
私は学生時代仙台で過ごしたので、秋田県の「仙」のつく地名に興味がある。
大仙市は、秋田県南東部に位置し、2005年に大曲仙北地域の8市町村が合併し誕生した市である。「大仙」の名前は、「大曲市」と「仙北郡」の頭文字からとった地名である。ちなみに大曲とは、雄物川の蛇行に由来しているという説と、地域に生息していた麻を刈ったことから「大麻刈」、それが大曲となったという説がある。
では仙北市とは。
仙北市は秋田県の東部中央に位置している。2005年、仙北郡角館町・田沢湖町・西木村が合併し仙北市となった(命名にかなり紛糾したようである)。
名前の由来は、「仙北」は古い資料では「山北」「仙福」「仙乏」と表記しているが、「仙」は仙台とは関係なく、「山」あるいは仙人の「仙」が由来とも考えられる。
一方で、奥州街道水沢宿(岩手県奥州市水沢)からと秋田県の仙北地方(横手方面)を結ぶ仙北街道がある。秋田側では「手倉越え」「仙北道」、また伊達領に通じる道という意味で、「せんだい道」「みずさわ道」などと呼んだことから、「仙台の北」という意味で「仙北」となったのではないかとも考えられる。
秋田市に河口をもつ雄物川の由来について。
諸説あるが、一説に、江戸時代中期の地誌に、貢物つまり年貢を当時「御物」と言い、それを運び出す川という意味で「御物川」とされたと言われている。
その他、上流に御膳(おもの)澤という地名があり、そこから御食(おもの)、そして雄物となったとの説もある。
次に山形について。
山に残る雪形が由来かと勝手に想像するもさにあらず。
山形とは、古代の出羽国最上郡、現在の山形市の南に位置する地域を、山のほうにある土地の意で「山方郷」と呼んだことに由来するとされている。ちなみに、野方や里方に対し、蔵王周辺を「山方」と呼んだと言われている。
その後南北朝時代に、斯波兼頼(しばかねより)がこの地を治めた際に「山形」という字になったとされている。
芭蕉の句「さみだれを集めて早し最上川」で有名な最上川について。
「最上」の名の由来には諸説ある。
まず、アイヌ語に由来するという説。
「もがみ」はアイヌ語で「静かなる神」を意味し、そこからきているという説。
その他、アイヌ語で庄内平野から上がった最上峡が、アイヌ語で「崖=モモ」の地であり、その「モモ」の「上【カミ】」にある広い盆地が「モモカミ」と呼ばれたことからきているという説。
また、前出の「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」という辞書には、「毛賀美(もかみ)」と書かれていて、これは「モー・カムイ=珍しい岩石の多いところ」という意味でこれが語源という説。
ちなみに最上川の流路延長(川の長さ)229 kmは、ほぼ一つの都府県のみを流域とする河川としては日本一である。
寒河江市も由緒ありそうな地名である。
ここは、平安時代に藤原家の荘園として開拓された。
一説には、相模の国(現在の神奈川県)の寒川(さむかわ)からの移住者が、この周辺の景色が郷里の寒川周辺と似ていたため「寒川」と呼び、ここを流れる河川が増水して入江になった名残で「寒河江」となったとの説がある。ちなみに「サガ」は朝鮮由来の名で、「相模」「寒川」に由来する地名と言われている。
また、鎌倉時代の学者大江広元がこの地の地頭に任命された際、流れる境川(集落間を流れる川の意)は京や鎌倉の川よりもかなり寒かった。ちなみに寒河江川は以前は境川だったとの説もある。自分の領地に優雅な名前をつけようとした大江は、「寒い河」に自分の名字の大江から「江」をつけ「寒河江」としたとの説もある。
その他、「さか(傾斜地)」と「え(川)」から、「傾斜地の川」の意から転じたという説、また、「さが(険しい地形)」と「え(川)」から、「険しい谷を流れる川」が語源との説もある。
さて、日本海に面する鶴岡市の地名は鶴ヶ岡城から来ている。
当地が、関ヶ原の戦いで功績のあった最上義光(よしあき)の領地となったとき、それまでの大宝寺城を、鶴が舞い降りたという吉事に因んで鶴ヶ岡城に改称したことが鶴岡の地名の由来とされている。
ちなみに、鶴岡市は市の面積では東北地方最大で、全国でも第10位の広さを誇っている。
酒田市の「酒田」は、古くは「砂潟」や「坂田」と呼ばれていた。
これには、「砂地の干潟」「狭い潟」「傾斜地にできた田」といった意味があるそう。その他、アイヌ語のサケ(鮭)トウ(海)、つまり「鮭の集まる海」からという説もある。
将棋の駒で有名な天童市の地名は、千数百年前、天から二人の童子が美しい笛や太鼓の音色とともに舞い降りてきて、その山が天童山と名付けられ、その四方の里が天童と呼ばれるようになったのが由来とされている。
羽黒山、湯殿山、月山を出羽三山と呼ぶ。
羽黒山の名は、7世紀、蜂子皇子が蘇我馬子から逃れている道中で道に迷った時、羽が黒い3本足の烏が飛んできて、羽黒山まで導いたことが由来になっているとのこと。
湯殿山は、1400年以上も前から湧き出る湯殿が参拝されてきたことによる。ちなみに出羽三山の奥宮として、「語るなかれ」「聞くなかれ」と戒められた神秘の霊場である。
月山は、この中で最も標高が高いが、その名は半月状の山の形から名付けられたそうだが、一方で牛が寝ているような形から「犂牛山」(くろうしやま)とも呼ばれている。
羽黒修験道では、羽黒山は現在の幸せを祈る山(現在)、月山は死後の安楽と往生を祈る山(過去)、そして湯殿山は生まれかわりを祈る山(未来)と見立てられている。
次に、その美しい山容から鳥海富士、あるいは出羽富士の名がある鳥海山。
その山名の由来は、山頂にある鳥ノ海湖からとする説と、鳥海弥三郎の誕生地とその領地に関係するとの説がある。
後者の鳥海弥三郎は平安時代中期から後期の武将で、全盛時代に安倍宗任(むねとう)と名乗っており、所領がこの地にあった。この安倍氏の出生地は宮城県亘理郡の鳥海の浦という所であったため、鳥海弥三郎宗任とも称していたため、この名に由来するとの説である。